〜氷の花〜

3
なぜだろう。
自分がこんなに変わるなんて...
他人と関わる事など今まで極力避けていた。
自分のことも別段どうでもよく、ただいつか奴にめぐり合ったならきっと斬る!そればかり考えてきたこの7年間。
その思いを果たした後も残る疑問。<自分は何者か?なぜ故に命を狙われなくてはならなかったのか。義父母までもが殺されなくてはならなかったのか...。>知りたい。でも知ったところで彼らは帰っては来ない。
だがそのために大切なもの〜自分を守り続けてくれる冠竜と、一人の男〜なくしたくはない。彼らは私を護ろうとするだろう。それこそ命に代えてでも。だが私だって護りたいのだ。彼らを、この命に代えても...。
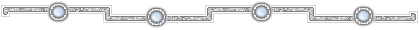
オーグ山脈の手前の森〜ヴォルドの森〜の手前で私たちはグロウから降りた。上空からはこの森の中の道は判別できなかったからだ。
周辺には町らしきものも、民家らしきものすらないことは上空から確認済みだ。
報告によると森への道は三本、そのうちの真ん中の道を奥へ入らなければならなかった。山々の連なりのほぼ手前ぐらいまで進んでいかなくてはならない。
「さすが、15年前の地図だな。わかりにくいぜ、これ。」
地図を覗き込んでいたジェイクは頭を抱えていた。
ディーノが依頼を受けた落ち合う約束の場所が書かれていた。オーグと呼ばれる山脈のふもとに広がる未開の森、深い森で有名で、入っていったものがまともに帰ってきたという話はあまり聞かない。平原を突っ切って帰る予定だったが、途中右手にずれていくと小さな山々を越えた先にオーグ山脈とその森はあるらしい。
「どうする?」
って、ジェイクがこちらを振り返る。
「そのままいくしかないだろう。報告どおりにな。」
道らしきものはあったが、町があるわけでもなく、ただ獣道のように開けているだけだった。しかしよく見ると石畳風にされている部分があったりと明らかに人の手が加わっている。(どこへ続く道として作られたのだろうか...)
ジェイクの身体が心配だったが、やはり鍛えられたガーディアンだ。歩きながら自分の身体の調子を整えていった。休んでばかりいては身体が鈍るらしい。
とりあえずは、まともにテントも張らずに野営を続けた。二人して背中合わせで眠ったりもした。遠くで獰猛な肉食獣のラビオの遠吠えが聞こえる時は、火をおこして交代で見張りをしたりする。初めての森では気は抜けない。やつらは夜行性なのだ。グロウも姿を見せなくなっていた。
ディーノ・クロスの残していた報告書はかなり詳しく、道に関してはかなり詳細な報告書が添付されていた。迷いつつ進んだ一行に比べ、報告書のまま突き進んだ我々とでは行程に差が出てくる。ディーノ達が四日かかったところを三日でたどり着いてしまった。
「カバスの樹と泉、ここに間違いないだろう。」
約束の場所というのはこの泉の手前にある大きなカバスの木(枝がそのまま地面へ伸びて根っこになる変わった樹木だ)のところだった。泉は崖のようになっている大きな岩棚の下にある。岩棚からは清水が流れ込んできているようだ。この辺は森といっても山々の手前、森の一番奥手になるので周りの風景もがぜん岩肌がむき出しになっていたりと、少々複雑な地形のようだ。
泉にまでたどり着くと、カバスの樹の根元の入りこんだ部分にテントを張った。
「この食料事情じゃあと7日が限界だろうな。」
荷物を紐解きながらジェイクがそう判断した。
「帰りの日程を入れて4日が限界だな。4日たったらどんな状態であってもここを立とう。」
4日、それが与えられた時間の限界。あとはなんの手がかりもないのだ。
(探せるのだろうか...?)
まだ明るかったので少し周辺を探してみる。私が隠れていたという岩陰を探す。このあたりは森といっても地層が隆起していて岩肌がやたら目に付く。
「記憶は?どうかな?」
ジェイクに聞かれるが、幼すぎる記憶は戻りかけもしなかった。
12年前、奴らに襲われた場所はここよりずっと手前の場所だったので、ひたすらジェイクに手を引かれて足早に通り過ぎた。かすかに身体が震えて足がすくみそうになったが何とか通り過ぎた。もう過去にとらわれていたくなかったし、なによりもジェイクがいた。
正直言って、あの時の記憶のほうが鮮明すぎて、二つ三つの頃の記憶など、どこを探しても出てこないのだ。
「とにかくひとつづつ探していこう」
それが結論だった。
その日は久々にテントで休めることになる。結構きつい3日間の行程だったので、今日は少し手を加えた食事で満服感を味わっていた。
泉の周辺にはなんら手がかりになるようなものもなく、私は少し焦りかけていた。ここまでくれば少しでも何か見つかるはずだと、甘い考えを持っていたようだ。
「明日もっと範囲を広げてみよう。」
食事の終わったあと、ジェイクが隣に腰掛けてきてそう言った。
二人とも疲れが出ていた。希望通りジェイクにも少しだけアルコールを許可した。さすがに怪我のことがあるのでジェイクの身体が気遣われたからだ。もちろん、薬草を入れておいたのだが...。まずいといいながらも久しぶりのお酒をジェイクはうれしそうに飲んでいた。
「リィンは飲まないのか?」
「飲んだことないんだ...」
「少し飲んでみればいい。よく休めるかもしれないだろ?」
昨夜はあまり寝付けなかったことに気づいているらしかった。あの場所を通ったことが影響しているのはわかっていた。思い出すまいとしてもよみがえってくる恐怖。胸の十字の傷とともに、身体を引き裂く痛み。ジェイクが抱きしめてくれてなかったら、そのまま朝を迎えていたかもしれなかった。何もせずにただただ肩を抱いていてくれた。
「じゃあ、少しもらおうかな?」
ジェイクが飲みやすいようにと、発酵酒の中にシロップをおとしてくれた。
お酒って、結構飲みやすいものなんだとその時は思った。
「ジェイク、暑くないか?」
しばらくすると顔が火照って、動悸が激しくなりつつあるのがわかる。お酒って後が大変なんだと後悔しても遅かった。
「リィン、大丈夫か?真っ赤になってるぞ。」
頭がぼーっとして、めまいまで感じはじめた。
「熱い...なんだか、息苦しくて...はぁ...」
いつもきっちりと結んでいる上着の紐までもがうっとうしく感じる。思わず自分の手で緩める。息が上がっていく。
「はぁ、はぁ...」
ジェイクが心配して覗き込んでくる。
「リィン...」
そのままジェイクの唇が私の唇をふさいでしまった。
「うっ、ん...くっ」
抵抗したくとも、手足にも力が入らない。動悸の音とともに頭が鳴り息苦しさが増す。
「うーーっ...」
ジェイクも、私があまりに苦しそうなのに気づいて唇を離す。
「なに、を...」
「ごめん、リィンの瞳が潤んであんまりにも色っぽいっていうか...」
我慢できなかったんだといった。こっちは苦しいのに!
「こんなに酒に弱いなんて思わなかったよ。ごめん、苦しいか?」
ジェイクは手を出すのはあきらめて、酔っ払いの介抱をはじめた。彼と旅し始めてから、休む時には鎧などははずすようになっていたから、今の私は紐で胸元を調節する白い上着と引っ掛けただけのベストといった服装である。これ以上緩められないほど、上着の襟を緩める。それでもまだ苦しいような気がして、ベストも自ら脱いでいた。
彼も気を使って背中などをさすってくれてはいたが、支えられてないと座っていることすらできない感じだった。
「暑い...、ジェイク...」
あんまり暑がるので彼は私を水辺へ連れて行った。ふらついて歩けない私を抱え上げて。わたしはただ彼の首にしがみついてるしかできなかった。
泉の側で私はなんとか自分で水を飲み、顔を冷やした。月明かりに水面に映し出された私の顔は紅潮し、唇は紅く半開きで、瞳はうつろな表情...
(これじゃ、ジェイクになにされたって文句言えないじゃ...あっ!)
「ジャバン!」
支えていた手が力なく崩れてそのまま泉の中へ落ちてしまった。
「おい!リィン、何してるんだ!酔っ払って水の中に入ったら溺れちまうぞ。」
急ぎジェイクが泉の中に入ってきて抱き起こそうとしてくれていた。
「ごめん、力が入らないの...」
ただただジェイクにしがみついているしかできない。
水の中に転げ落ちた時に鬘は脱げ、銀髪が身体を這うようにへばり付いている。自分の胸元を見ると白い上着は濡れて透けてしまっている。
「やっ!...」
気がついて胸元を隠そうとしがみついた手を離すと、また足元が崩れ落ちそうになる。
ジェイクの腕に力が入る。
「ごめん、俺も限界...」
そのまま泉の中に倒れこむようにして二人落ちる。
浅瀬に二人座り込んだ形で抱き寄せられ、ジェイクの唇が重なってくる。抵抗することもできずただそれを受けていた。
ジェイクの手がはじめて私の素肌に触れようとしていた。濡れて透けた上着は肩から落とされあらわになった私の素肌に...。
「リィン...愛してる。」
ジェイクが耳元で囁く。熱した頭はぐるぐると回っていて、もう自分がどこにいるのかわからなくなっていた。
Back・Next
>Home>NovelTop>Top


![]()