〜氷の花〜

6
「おはよう、リィン」
ジェイクの鳶色の瞳が優しく微笑んでいる。日が昇るまでのわずかな時間、わたしはしっかりと眠ってしまっていたらしい。ジェイクの胸の中で...
座ったままもたれていたので急ぎ立ち上がる。
「おはよう、ジェイク?」
苦笑いして微動だにしないジェイク。
「どうしたの?」
「ん、ちょっと半身しびれちゃってて、立てないや。」
どうやらわたしのせいらしかった。
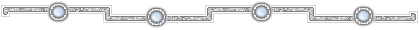
その日も、また泉の底を調べ続けた。
あたりを調べ始めて三日目、何度か交代で潜ってみる。けれど、あの紋章はびくともしない。
「せめて俺が思い出せればなぁ...」
ジェイクも絶えず思い出そうと、努力はしているらしかった。どこで見たかはうつろながら自分の家のどこかと覚えてはいるが、それ以上は思い出せないでいるらしい。
「この文字が読める人もどこにいるのか...」
「そりゃあ、うちの探査部門に頼めば調べてはくれるだろうけど...」
ジェイクはガーディアンの内情にもすこぶる詳しかった。依頼を受けても、事件に巻き込まれたり、ガーディアンたちが疑われたりした場合にも動く部門らしいのだが、16年前のディーノの依頼の時も、調査が行われたらしかった。ジェイクはそのときの資料も手に入れるつもりだったらしいのだが、今回はガルディスに頼んだので、ちょっと無理だったそうだ。
さすがに今日は裸で潜るわけにもいかず、私はさらしをまいてはいたが、ズボンでは水を含んで重かった。
「リィン、無理するな。俺が潜るからお前はここで休んでいろ。」
顔色のよくない私にきつい口調でジェイクが命令してくる。よほどひどい顔をしてるんだろうな、今の私...。時間とともに焦りが突き上げてくるのだ。
(時間がない...このまま何もわからないまま帰らなければならないのか?)
次はないような気がした。この次ここに来る時はおそらくおそらく一人だろう。そこまでジェイクに甘えられない。独り...グロウがいなければ、ジェイクがいなければ、私は独りなのだ。グロウのいる安心感、ジェイクの胸の暖かさ、知ってしまえばもう知らなかった頃には戻れないのだろうか?
たったひとりでこの謎と向き合えるのだろうか?せめてもう少し、何か手がかりがつかめれば...。ディーノに拾われるまでの私、本当の両親は?私はそれが知りたいだけ。
でも奴は───ディーノを殺したあいつは、何かを手に入れたがっていた。何を?そんなに価値のあるもの?何人も殺してまで手に入れたがるようなもの?それがこの背中に刻まれているのだろうか...
少し貧血を起こしかけていたのだろうか、木陰で休みながらそのまま眠ってしまっていた。
「ギィーッ!」
(グロウ?)
目覚めかけた視界の中に大きな影が舞い降りてくる。
「グロウ!!」
私は駆け寄り抱きついた。ひんやりと冷たい冠竜に飛びついて。
「かえって来たんだね?どこに行ってたんだ?」
「グルルル...」
グロウは軽くのどを鳴らして答えていた。
「リィン様...」
しわがれた声が私を呼んだ。
振り向くとそこにはおばばが膝まづいて控えていた。
「おばば、どうしたんだ?グラナデ王国でしばらく専属やってるんじゃなかったのか?」
森からも人がやって来た。
「ガルディス!」
泉から上がったジェイクが駆け寄っていく。
「よお!ジェイク、なかなか帰ってこねぇと思ったら、こんなとこで二人よろしくやってたのか?」
「なんだよ、ガルディス!冷やかしに来たのか?」
(おい、否定しろよ...)
相変わらずの二人のやり取りに閉口しながらも、私は目の前にかしづいたままのおばばを見ていた。
(どうしたんだ?おばば、いつもとちがう?)
「あの報告書を送れば、おそらくここへ来るだろうと狙いは付けてたんだがな、さすがにあの冠竜をつかわれちゃ追いつけなくてなぁ。」
ガルディスはトルバを駆ってきていた。もう一頭のトルバ、そこにはもう一人の男性の姿があった。
「総帥!」
ガーディアンの内情にうとい私でもさすがに知っている。わがガーディアンの総帥の姿がそこにあった。齢はすでに50を越えているとは聞いていたが、見た目にはまだ十分戦士で通る鍛えられた体躯と、厳しく鋭い眼差しは英知の光を宿していた。私は国に帰り着いた後、謁見し、ガーディアンとして認められた折にはじめて顔を見たが、その時柄にもなく緊張したのを覚えている。
「げっ、親父!」
(親父??)
ジェイクが叫ぶなり後ずさり始めた。それをガルディスが引きずって総帥の前に連れて行く。
「怪我はもういいのか?ジェイク。」
総帥の低く響く声は優しさを含んでいた。厳しい瞳も和らいですらみえた。
(ジェイクが総帥の息子?)
「あぁ、もうなんともないさ。いえ、もう大丈夫であります、総帥。このたびはすぐに戻らず申し訳ありませんでした。これはすべて私が計画したことであります。」
ジェイクは身を正して答えていた。
わたしは呆然と彼らのほうを見ていた。
「リィン様、お召し物を...」
「あぁ、そうだな。」
私の格好といえば、一眠りしている間に乾きはしたものの、さらしをまいたままの格好である。急ぎおばばの差し出してくれた服を着込んだ。まだかしづくように膝まづいている。
「どうしたんだ?おばば。」
おばばの視線が私の頭上にあった。
(しまった!髪を...)
誰かが来るなんて考えてなかったし、さっきまで水中に潜ったりしていたのですっかり鬘を被るのを忘れていたのだ。
「リィン・クロスか?」
総帥がこちらへと近づいてくる。
「はい。総帥!」
おもわず敬礼姿勢をとる。
「この度はみごとディーノ・クロスの敵が討てたそうだな。」
「ありがとうございます。それもすべてジェイクが、ジェイク・ラグラン殿のご助力があってこそです。そのために傷を負わせてしまい申し訳ありませんでした。」
下げた頭をあげよと言われ見上げると、そこにはジェイクと同じ鳶色の優しい眼差しがあった。
(やはり親子かな?ジェイクと似てる...雰囲気というよりも瞳の柔らかさがおなじだ。)
「いや、どうせあやつが好きでやったのであろう。どうも無鉄砲なところが治らん。」
みごとな口ひげで表情は読み取りにくかったが、優しい口調であった。
「あの、総帥はジェイクの父君でいらっしゃるのですか?」
「愚息が迷惑をかけたな、リィン・クロス。」
「けどなんで総帥自らこんなとこへ出てきたんだよ?」
ジェイクが後ろから私を庇うように一歩前へ進み出る。彼の肩影にすっぽりと入ってしまう。
「理由か、理由はその銀の髪だな。」
総帥の言葉に、ジェイクはなおのこと私を自分の後ろへとやった。
「ごめんよ、俺が見ちまったんだ。リィンのその銀髪のところをさ。」
「まさか、ガルディスてめぇあん時のぞいてたんじゃ...」
すまんとガルディスが謝った。グラナデ王国で、私が銀髪になったのはジェイクの見舞いに行った時だけだ。ジェイクとのキスシーンをしっかりと見られてたってわけだ。
「リィンの銀髪、そしてディーノの事件。15年前のこの地での任務のことを調べていたそうじゃないか。ガルディスから色々と報告を聞いてな、急ぎ駆けつけたわけだ。」
総帥は、ジェイクたちを軽くいなすとおばばの方を見やった。
「そうなると、このおばばを呼び戻さなくてはならんかったのでな。実はそこの冠竜がおばばを迎えに行ってくれていたのだよ。」
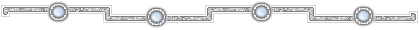
「まず、ジェイクも気づいてたとは思うが、ガルディスは昔から私の直属の部下でな、お前がガーディアンになったときからお目付け役として側に付かせていた。」
「あぁ、気づいていたよ。」
とジェイクは答えた。
「うむ、まあこういう奴だから頼みもしないのにお前の教育係まで買って出て、いらぬことまで色々と教えておったらしいがな。」
総帥がちらりと隣のガルディスをみやる。彼はやたら頭をかいては下を向いてしまった。
「そして、15年前のディーノの受けた依頼は、実はあれは私が出したものだったのだ。」
総帥の目は軽く周りの景色を見回しながらゆっくりと言い放った。
「わたしは、ここに来たことがあるのだよ。25年ぶりになるがね。」
その目は懐かしさをたたえていた。
「23年前、私は銀の王国を探せという依頼を受けて、このオーグ山脈をに入り、山脈を抜けていた時落雷にあい、負傷し、目が覚めたとき私は助けられ治療を受けていた。その治療をしてくれたのがこのおばばで、助けてくれたのがジェイク、お前の母アイリーンだったのだよ。」
ジェイクの目が点になっていた。彼はその事実をまったく知らなかったのだ。
「私はそのまま彼女を連れて国へもどった。その時ここを通ったのだよ。『銀の王国は見つからず』と依頼主にも報告した。だが銀の王国とは、私の助けられたところだったのだ。私は銀の一族のひとりを連れて出る代わりに約束をした。『銀の王国の秘密を守ること、ひとたび危機に見舞われたときには助力を惜しまぬこと』とな。そして15年前、このおばばが助けを求めてやってきた。『王国が危ない』とな。しかし、その時私は国外へ遠征しておりすぐにはここに向かえなかった。そのためにディーノ・クロスが私に代わってここへ向かってくれたのだ。ただ、すべての内情を話すわけにもいかず、依頼という形でここへ向かわせたのだ。ここへ落ち延びてくる銀の王国の生き残りを保護せよとな。」
総帥の郷愁の目は泉の方を見つめていた。
「あとはこのおばばがお話しましょう。銀の一族とは、銀細工や宝石の加工にかけては右に出るもののない技術をもった一族で、私もその一人でございます。私どもは主に森の奥、地下階層に隠れ住んだりしておりました。細工のための宝石や、貴金属を多く所有するため野党などから狙われやすく、身を隠すためにその所在を一切明らかにはしておりませなんだ。王国崩壊の後には、大国のお抱えになったり、商人と手を結んでギルドを作ったりしておりますがの。昔は一族全員が銀の髪をしておりましたが、今では外の血が入りわずかな者を残すのみであります。銀の髪の者は王族として一族が所有する稀有な価値をもつ『この世の奇跡』と呼ばれる宝石の数々を守ることで一生を終えるのです。そのなかでも、十年に一度占いにより選ばれた銀の髪の赤子の背に、奇跡の宝石の隠し場所を示す隠し彫りを入れるのです。リィン様、あなた様の背中に隠し彫りはございませなんだか?」
おばばのことばに素直にうなづくしかなかった。
「そうか、わたしはディーノからは君に関しての報告は、何も受けてなかったのだよ。よほど手放せなくなっていたのだろうな。こんなことなら、ディーノにだけでもすべて話しておくんだったよ。決して口外しないというのが約束だったものでな、かたくなに守りすぎてしまったか...」
総帥が優しい目でこちらを見ていた。
「親父、お袋が銀の一族って言ってたよな?」
今までただ黙って聞いていたジェイクが口を挟んだ。
「あぁ、お前の母親は王族の一人だが、髪の色がお前も知っての通り黒髪だ。だから王族からははずされてはいたが、当時の国王の娘でもあったのだよ。」
総帥、はジェイクのほうを向いてそう言った。
「はい、国王サーネイル様の一のご息女であられました。そして裏切り者のレイノールは王族の一人で、アイリーン様の許婚と決められたお方でした。」
おばばの言葉に、ジェイクはばつが悪そうにこちらを見てため息をついた。
Back・Next
>Home>NovelTop>Top


![]()
![]()