〜氷の花〜

7
泉の側で五人は車座になって話し続けていた。銀の王国の秘密について。
「国王様ご夫妻には12人のお子様がいらっしゃられましたが、とうとう銀の髪のお子が誕生されませんでした。リィン様の母君は銀の髪ではあられませんでしたが、リィン様が銀の髪を持って生まれ出でられた時より王族入りされ、国王弟君の嫡男でもあられたカーナイブ様の婚約者となり、背中に秘密を背負われたのであります。」
「では私の両親は?わからないのですか?」
「母君は王の后の末の妹君ナイジェル様です。しかしナイジェル様は最後まで父君の名を語らぬまま産後のひだちが悪く亡くなられてしまいましたのじゃ、14歳であらせられました...。」
「そうですか。父の名もわからず、母も亡くなっているのでは仕方ないですね。」
(銀の王国へたどり着いても、秘密を解き明かしたとしても、もう私をこの世に生み出してくれた両親とはもう会えないのか...)
かすかな落胆が生まれた。もうとうにあきらめはしていたのだが、少しは期待していたのだろう。ジェイクの手がいつの間にか私の肩に回されていた。
「銀の一族は各地へ散らばりましたが、銀の髪の王族一族は奇跡の宝石のありかを吐かせるためにひどい拷問を受けたとも聞いておりまする。もう一人背中に秘密を持っておられた姫君は、賊の手に落ちる前に自害されました。今現在残っておられる銀の髪の王族はリィン様、あなた様お一人でございます。」
「私一人...」
「はい、このまま『奇跡の宝玉』を眠らせることはできますが、またリィン様が狙われることは必須。ならばガーディアンが警護する我国へ持ち帰って保管することもできようとザナックス殿がおっしゃられております。銀の一族も、国で庇護しようと申し出てらっしゃる。王国が消滅し、残る王族はリィン様のみならば、ご決断はあなた様にしていただくのが筋かと存じます。」
「私が?決めるのか?」
「はい。リィン様のお心のままに。おばばは、王族に使えし者。今はリィン様にお従いいたします。」
「もう存在しない王国や、王族に固執する必要はない。この銀の髪も私一代で終わるかもしれんしな。」
(髪の色だけで決められてもしょうがないんだが...。)
「総帥、お言葉に甘えてもよろしいですか?『奇跡の宝玉』なんて欲しくもないし、ガーディアンの国の庇護の下甘えて暮す気もありません。が、現在阻害されたり、行き場を失っている一族のものがいれば居場所を与えてやっていただけますか?」
「もちろんだ、ただし銀の一族、その特殊な技術はしっかりと商工の部門で役立ててもらうつもりだ。我国へ忍び込んでくる無謀なものもおらんだろうしな。」
総帥は口元でにやりと笑って見せた。
(やっぱり親子だ。しぐさが同じじゃないか...)
ほっとしたような、安堵感を覚えた。
(信じていいんだ。この人たちを。)
昔の自分なら頭から疑ってかかり、人に任せるなんてこれっぽっちも思わなかっただろうに。
「では、すべての財宝を取り出し、ガーディアン総帥に預け銀の一族におって還元していただきたい。よろしいか?」
皆が一同に頷いた。
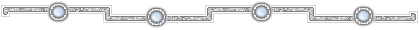
「鍵はここに、ザナックス殿が奥方より借り受けてこられたものがございます。これで泉より銀の王国へは入れますが、財宝のありかはこのおばばにもまったく見当がつきませぬ。リィン様、背中の刺青を見せていただきたいのだが...いかがでしょう」
おばばの問いにジェイクが嬉しそうに自分が写し取った紙を取り出していた。
「ちゃんと写してあるさ。ほれ、これでわかるだろう?」
「....」
「おばば?」
「ジエイク殿、これでは読めぬわ...」
「うわ〜〜、これじゃ知ってる字でもわかんねぇよ!」
ついでガルディスが口を挟む。ジェイクがつかみかかっていくが、いつものじゃれあいだ。ほおっておこう。
「すまないな、こいつは昔から字や絵を書くのが苦手でな。」
総帥が苦笑いしている。
「しかし、ジェイク殿、どうやってリィン様の背のものを写されたのじゃ?」
「えっ?」
ジェイクと私は急激に頬が赤くなるのを止められなかった。
「いや、俺がリィンに酒飲ませちまって、それでまぁ、暑がってだな、その、み、水の中に落っこちまって、えーと、そん時に、まぁその見たって言うか...」
(ばかジェイク!なにをそんなしどろもどろになって...もうっ!)
ガルディスがもろニヤニヤと笑ってこっちを見ている。総帥は比較的冷たい視線だ。
「ジェイク、リィン殿に不埒なまねはしておらんだろうな?」
「げっ、親父...いやその...」
(だめだ...これじゃ...)
何もかもばらしてるのと同じだ。私はジェイクの腕を軽くつねると一歩前へでた。
「酔って泉に落ちた私を介抱するときにジェイクが見つけてくれたんです。出なければ気づかないままでした。きっとお酒を飲めばまた出ると思いますが、私は生憎アルコールには弱い体質らしく、前後不覚になってしまいます。発酵酒をお持ちであらば飲みますが、酔った自分を見られるのが恥ずかしいので...その、ジェイクが付いててくれるならなんとか...」
腕をさするジェイクを尻目にガルディスが嬉しそうに乗り出してくる。
「発酵酒ならたんまりあるぜ。」
テントの中はジェイクと二人だけだった。
酔いが回った自分と、醒めた後の最悪さを思い出すと二度とは飲みたくなかったが、この場合拒否はできないだろう。もうひとつの方法は皆のいる前では恥ずかしくてできっこないのだから...
「飲むぞ。」
「あぁ、大丈夫か...じゃないよな。俺が付いてるから頑張れ!」
なにを頑張るんだか。ジェイクの妙な励ましの中酒瓶に口をつけた。
「リィン?」
かなりの量を口にしたかもしれない。まわってはきてるのだろうけれども、妙に頭が冴え冴えとしている。緊張感だろうか?
「どうかな?でてるか、ジェイク?」
私はすでに上半身は何も身につけていない。ただ恥ずかしいので、上着で胸元を隠してはいるけれども。
「まだでてこないな...体は酔い始めて熱を持ち出してると思うんだが...」
「もっと飲まなきゃいけないかなぁ?」
「後が大変だぞ、いいのか?」
もう少し発酵酒を口にした。
「リィン、ちょっとだけ触れてもよかったら、その...早く出ないかな?」
(触れるって...)
そんなことできるはずがないだろう?だけど思考能力は徐々に低下し始めてる。
「ん...」
うなずいていた。自分でもなぜだか判らないほど素直に。目はうつろで焦点も定まらないままだし、だんだんと力も入らなくなってきてる。
「リィン、おいで。」
差し伸べられたジェイクの腕の中へ自分を預けた。すぐさま優しく抱きとめられ、ジェイクの唇が落ちてくる。口元に、首筋に、そして胸元に...
「あっ...ん」
自分でも信じられないぐらい艶っぽい声が漏れていく。
(やだ、恥ずかしい...)
羞恥心とは裏腹に身体は彼にすべてを預けてしまっている。
「ジェイク...っ」
ジェイクの指先が背中から腰の稜線をなぞっていく。その奇妙な感覚に敏感に反応しながら私の頭は白くぼやけて行った。
「リィン、出てきたよ。」
私はすでに力が入らなくなった腕を動かして、なんとか上着を胸元へ引き寄せた。
「親父達を呼ぶよ?」
力なくうなづく私を支えたまま、ジェイクが外に向かって彼らをテントへと呼び込んだ。
「おばば?なんて書いてあるのだ?」
「うむ...、《光射す導きの胸元に我は眠りて。その番手を解き放たん。さすれば道は開かれる。》そしてこれは王国の紋章の銀細工の文様だが、本物とはちと違うようじゃ、この小さいのは鍵じゃな、この文様も...誰か正しく書き留められるかの?」
「こうすればいい。」
総帥が薄手の布地を私の背にかぶせた。
「ガルディス、お前確か絵心があったな?写せるか?」
「あぁ、かまわないか?リィン殿」
私は皆に背を向けたままうなずいた。力の入らぬままジェイクに身体を預けていた。
「あっ!」
背を這う筆の感触は先ほどのジェイクの愛撫で敏感になり始めていた身体には刺激的すぎた。ジェイクの腕が、私の頭と身体を身動きできないように羽交い絞めにしている。
動かぬように耐え続けていた。この神聖な拷問から...。
「おばば殿、これでよろしいかな?」
「おぉ、上出来じゃ。先ほどのはほとんど読めんかったからな。」
「ちぇっ。」
ジェイクはおばばに悪態をつくと、全身ぐったりさせた私を抱き上げてテントを出た。
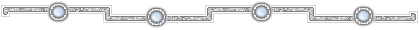
すっかり酔いが回って眠ってしまっていたらしい。泉まで行って火照りを冷やしたのは覚えているが、その後はまた記憶がない。
目が覚めるとテントの中で、ジェイクが心配そうに覗き込んでいた。
「これ、おばばが飲んどけってさ。」
出されたのは茶褐色の丸薬だった。
「あぁ...ぐっ!」
身体を起こしたとたん頭の中が、ががんがんと音を立ててるようだった。のどの奥からは苦いものが上がってくるような、むかむかした感覚。急ぎ出された丸薬を水で流し込む。
「やっぱりひどいみたいだなぁ。」
「皆は?」
「外で謎解きしてるよ。起きて大丈夫か?」
「ん、仕方ないだろ。あっ!」
立ち上がりかけてしっかり足をとられる。なんて無様なんだ!ジェイクの支えでテントから出る。
「リィン殿お体大丈夫でございますか?」
「ありがとう、おばば。薬もらったから...」
泉の周りでは三人が車座になって私の背の写し絵とにらめっこを続けていた。その前にはジェイクの母君が持っておられたという鍵と、おばばが持っていた銀の王国の紋章入りの薬入れが置かれていた。
「何か判った?」
ジェイクが写し絵を覗き込んでは気軽に聞いていた。
「細かい模様だな〜〜。リィン、二日酔いで見たら目が回るぞ!まるで迷路みたいだからな。」
「ほんとだな、どれも模様が少しずつ違うの...今見るのは辛いな。」
「迷路...もしかしたら....ガルディス殿!」
おばばがガルディスに写し絵を突きつけながら、彼女にしては珍しく大きな声で言った。
「この三つの模様を同じ大きさに写しなおせますかな?」
ガルディスはうなづくと、平らな板の上で、紙とペンを器用に滑らせて三枚の絵を慎重に書き上げた。
その間には、おばばの薬が効いてきたのかかなり楽にはなってきた。
「いかがですかな?」
ガルディスはその三枚の絵をおばばの前に並べた。
「うむ...」
総帥はその隣で黙って腕組みしたままそれを見ていた。
「本当に迷路だよな。ちょっと中途半端だけど...重ねたらはっきりしそう。」
「それじゃ!!」
おばばがジェイクの言葉にすばやく反応していた。三枚を重ねると日の光にすかして見せた。
「おぉ!見よ、これが地図となるのだろう。ザナックス殿、地図と鍵が揃い申したぞ。」
「うむ、ジェイク。」
「あぁ。」
「私はこの泉の前でお前達を待とう。リィン殿とともに銀の王国へ行くが良い。」
Back・Next
>Home>NovelTop>Top


![]()
![]()