〜氷の花〜

8
おばばも水中を通って行くことを断念し総帥と二人岸辺に残ることとなった。
ジェイクとガルディスが先に潜り鍵を開けた。長年使用されてなかっただけに、少々の手間はかかっていたみたいだ。私も一緒に潜ると言ったのだが、ジェイクに激しく拒否された。
「ゴゴォーーッ」
突然くぐもった音を立てて、水面に波紋が大きく広がり、今まで凪いでいた泉に突然流れができた。岩盤にむかって水が流れ込み始める。
「ぷはっ!」
二人が揃って水面に顔をだした。
「リィン!さぁ、行こう。」
ジェイクが手を差し伸べる。振り向くとおばば達はうなづいて見送っていた。
荷物を持つと先にガルディスが水中へと姿を消した。
私もジェイクとともにその後を追った。
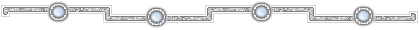
水中深く潜ると、岩盤の鍵穴のあった辺りにぽっかりと空洞ができていた。水の流れはそちらへと向かっていたので自然とその空洞へと入り込めた。一瞬あたりが暗くなったように思えたが、すぐ先の水面に明るさを感じて三人はそこを目指して泳いでいった。
「ここは...」
明るくなった水面に顔を出すと、そこは洞窟の中であった。ほんのり明るかったのは回りに生えている光ごけの一種だろうか?その明るさのおかげで視界には苦労しなくてすみそうだった。水面はそこで途切れ、岩場はそのまま洞窟の奥へと続いていた。
三人は水から上がると、固く縛った防水の袋からそれぞれの着替えを出して着込む。
洞窟の奥も光ごけで通路は確保できそうだった。
「これがおばばが言っていた《通路》だな。ここから言われたとおりに抜けると銀の王国へたどり着くってわけだ。ただしこの地図の迷路はこの地下通路の中のことだ。どうするリィン、先に宝玉を捜すか?それとも銀の王国へ行ってみたいか?」
ジェイクの問いかけに心は一二もなく決まっていた。
「銀の王国へ、かまわないか?ジェイク。」
二人がうなづいて答えてくれた。
おばばに教えられたとおり三番目の角を右に回り一つ目を左、まっすぐすすみ五つ目を右二つ目を左そしてまっすぐ。
そこにはただの岩壁しかなかった。壁の左下の小さな岩をどけると、泉と同じ鍵穴が出てきた。
「よし、開けるぞ?」
ジェイクが再び同じ鍵を差込回すと岩壁がゆっくりと右手の方へ開いていった。
「あっ!」
(眩しい!!)
それは陽の光の眩しさだった。慣れるまでの間しばらく三人は立ち止まっていた。
「ここが、銀の王国...。」
木立の中に石の建物がいくつか並んでいた。王国というよりも隠れ家なのだ。
「もともとたくさん住んでいたわけでもなく、王族とその一派のみで、他の一族はそれぞれ国外で暮していたと言ってたものな。本当に小さいんだ...。」
ジェイクは先に一人奥まで進んでいった。木立のすぐ先は岩壁になっていて、ここだけ本当に切り抜いたかのような別世界だった。
「定期的に訪れる一族の持ち寄るもので生活していたんだろうな。」
わずかな畑の後をガルディスが見回していた。
私は建物の中で一番大きな建物の中へと足を踏み入れていた。
「うわぁ...」
ジェイクが感嘆の声を上げた。
王宮であっただろう建物の成れの果てであった。たが大理石を使ったその建物の内部は老朽化することなく磨かれた美しさを保っていた。
入り口、エントランスの部分はこじんまりとだが、訪れる人の目を楽しませる程度の凝った銀細工の調度品がいくつか残されていた。
(盗賊に荒らされたってわけでもないんだ。)
突き当たりの壁には大きな鏡が掲げられていた。、もちろん回りに豪華な銀の細工がしてあった。その下のスツールの上には倒れた置き鏡があった。
リィンはそれをそっと置きなおした。そこには銀の髪した自分の姿が映っている。
(この鏡に私以外の銀の髪の人間が映ることはもうないのだろうか?)
長い間ここに集う一族の姿を映したであろう鏡に郷愁を感じながら、しばらく眺めていた。
「おおい!」
各部屋を調べていたガルディスが呼ぶ声が一番奥の間から聞こえた。
「どうした?ガルディス」
ジェイクが続いてその部屋へ足を踏み入れた。
「うっ...」
「どうした?」
奥の間で見たその風景は...。
幾体もの白骨であった。
重なり合うようにくずれた何体もの人であったもののかけらは、誰に葬られることもなく何年もの間この王宮のこの部屋の中で眠り続けていたのだ。
「自害したか殺されたかはわからないが、残った王族の人たちだったんだろうな...」
ジェイクがそう言った時には、ガルディスが胸に手を当てて頭をたれて喪の礼式をとっていた。
「ジェイク、この方達を土に返してあげられないかな?」
「そうだな...」
ガルディスもうなずき木立の一番端のほうに土を掘りすみやかに埋葬した。
「本当に私だけなんだ...。」
悲しい実感が沸いてきて、一人でいるのがたまらなかった。
後ろを振り向くとジェイクがすぐ側に立っていた。私は少し後ずさりして、彼の胸に背中を預けた。後ろから暖かく抱きしめられて、私はほんの少し安堵感を手に入れていた。
「さてと、そろそろ謎解きへ向かうとしねえか?」
ガルディスに促されて洞窟の通路へと戻っていく。
「スタートがどっちかだよな?」
「へっ?」
ジェイクが情けなく聞き返す。
どうやら頼りになるのはガルディスのほうらしい。無骨な風体とは対照的に器用な手先と考える力を持っているらしいし。
「王国の人間の手によって探し出されることを前提にしてあるから、もちろんこちら側がスタートだと思うが?」
「やはりな、こちらからということでやってみようか。」
地図をはさんで打ち合わせをする後ろでジェイクがかなり遅れて『なるほど!』と納得していた。
(遅すぎるよ...)
「三枚の文様を重ねて出来た迷路の地図はこの洞窟の通路であることはわかっている。問題はこの《光射す導きの胸元に我は眠りて。その番手を解き放たん。さすれば道は開かれる》がどの場所のことか...。」
ガルディスのもっともな言葉にジェイクはひたすらうなづいていた。
「光といっても、洞窟の中は光ごけの明かりのみだし...射すほどの光の強さはないし...」
二人して地図を前にして悩んでいるとジェイクの声が洞窟の中から聞こえた。
「なぁ、通路の角々にこんなのがあるよ〜〜」
駆けつけた先には砂埃を取り払うと小さな鏡にも見える銀のプレートが岩肌に埋もれながらもその姿を現していた。
「ちょっとだけ中に入ろうと思って壁に触れたらここだけ冷たく感じたんだ。」
(ジェイクはとんでもなく強運か、感がいいかだな...)
「リィン殿、地図の中でもその角の壁には印が入っていることになります。」
「ではその印の入ってる角を全部あたろう。」
三人で手分けして見るとその角々に、上下の差はあっても同じような銀のプレートが隠れていた。軽く磨いてみると王宮の銀細工の鏡ように輝きはじめた。
「これで全部だな。結構あったぜ。」
ジエイクが最後のプレートを磨き終えて洞窟から出てきた。
「こっちから見てもあんまりわかんないな。光ってでもくれればわかるのになぁ。」
ジェイクが後ろを振り向きながら、リィンの側へ戻ってきた。
ガルディスもこちらから洞窟の方をいろんな角度から眺めている。
(光射す、導き、か...光、そうだ!)
「リィン、どこへ行くんだ?」
いきなり踵を返して駆け出した背中への問いかけに答えもせず小さな王宮へと戻りすぐにまた洞窟入り口のの前へと帰ってきた。
「それは?」
「王宮にあった銀細工の鏡だ。これで、こうすると...」
私は鏡を陽の当たる下にかかえたまま、その光を反射させて一番入り口に近い銀のプレートに当ててみた。その光の筋はまた銀のプレートに当たって次々と湾曲していった。
しかしすぐにずれてしまってなかなかうまくいかない。
「リィン殿、私がやってみましよう。ジェイクとその光の筋を追ってくだされ。」
ガルディスが替わって鏡を持つと、しっかりと固定しながら起用に光をプレートに当てていった。
「リィン、この光を辿っていこう。」
次々とプレートに当たって光は進んでいく。
広くない通路を二人して追っていくのはもどかしいものがあった。
(どこなんだ!)
何度も何度も洞窟内の通路の角を右へ左へと曲がる。そしてその光の筋は壁の一つに当たっていた。
「おっ、この壁なのかな?」
ジェイクが剣の柄でたたいてみた。隅々まで調べては見るが、ただの厚い岩盤だった。
「ここは洞窟の中でも端のほうだよな。ここより向こうに通路はないし...」
ジェイクはきょろきょろと見回したりせわしなく動いている。
「胸元...。光射す導きがこの光なら、胸元はどれになるんだろう?」
「胸元なぁ...。俺の想像力じゃ精々リィンの胸元を想像するぐらいで...」
「ばか!」
近づいて覗き込んでくるので軽く肘鉄を食らわせる。大げさに痛がるジェイクをよそに岩盤の前に立ってみる。光はまだ注がれている。
「リィン、こっち向いてみろよ。」
「えっ?」
「いいから、その場所でこっち向いて、光が胸元に来るように身体を動かしてみて!」
やけに真剣な声で言ってくるので思わずそのままジェイクの指示に従う。
「そこで止まって!」
ちょうどその光が胸の胸腺に当たるところで立ち止まる。ジェイクが近づいてくるのをそのま待つ。
「最後の光は意外と下のほうからだからな、ここまで前に出ないと胸元にはあたらないだろう?そのままだと壁に当たる光は俺の頭の高さぐらいになってしまう。」
「うん、胸元って言うのにこだわればそういうことになるな。」
「だろ?俺個人としてはこだわりたいからね♪」
「ジェイク〜〜!今はこだわらなくていい!」
伸びてくる手をぴしゃりとやる。せっかく見直しかけたのに...
「でもさ、ここってわけでもなさそうだから...リィン鏡か剣でその光を反射させるとしたらどうかな?」
腰の短剣を抜くと胸元にかざしてみた。
私の向かっている壁をジェイクが丹念にしらへべて見ると同じ銀のプレートが埋め込まれていた。急ぎジェイクがそれを磨き、そこに光を当ててみる。
その光の先は、最初に当たっていた壁とは隣になる別の壁へと伸びていった。
「この壁かな?それともこの光の当たってるところに...あれ?」
「どうした?」
「ほんとにあったよ。」
ジェイクが壁の右隅に当たった光の位置を調べていたらはめ込んであった石が外れて鍵が出てきた。その右手には大きめの鍵。
「でも鍵だぜ。だったらどこにあるんだろうな、この鍵の穴は?」
(ジェイクったら...)
まるでおもちゃを見つけた子供のように好奇心いっぱいの目をしてあちこちとしらべ廻っている。もともと財宝だの宝玉だのには興味はない。おまけに動くなといわれてるわたしは、ジェイクの姿を目で追っていた。口元には微笑がしらずしらずに浮かんでくる。
(愛しいというのは、こういった気持ちをいうのだろうか?
「リィン?」
「えっ?」
「少しずれてみてくれって言ったんだよ。この光の当たってるところにしるしいれてみようと思ってさ。」
「あ、あぁ」
私が動くと光は最初に当たった壁の上に戻る。
「ここだったんだ。」
「ここ?」
「鍵穴があったよ。ほら!」
光の射しているところには石で鍵穴が隠されていた。ジェイクの隣に並んで覗き込む。ちょうどジェイクの目の高さなので少し背伸びをしないと見えにくい。
「本当だ。開けてみるか?ジェイク。」
覗き込んだまま聞き返す。
「う〜ん、いつまでもガルディス一人に鏡持ちさせてたら後でおこるだろううしな。呼んでくるよ。」
「あぁ。そう...っ!」
間近に会ったジェイクの顔が近づいてきて、そのまま唇を塞がれてしまった。
「二人っきりはここまでだろ?」
ジェイクは軽く方目をつぶるとそのまま通路の奥へと駆けていった。
Back・Next
>Home>NovelTop>Top


![]()