〜氷の花〜

9
すぐにジェイクがガルディスを伴って小部屋へと戻ってきた。
それを私はちょっと冷たい視線で待っていた。その目線を無視して目の前を通り過ぎる。
「あれ、怒ってる?」
彼はしらっと言っては鍵穴の前に立った。
「さぁ、開けるよ。」
ジェイクが見つけた鍵を鍵穴に差し込む。
「ガチッ!」
鈍い音がした。
「あれ?どこが開いたんだ??」
「音はこの壁からしたんだがな?」
「リィン?君の後ろ...」
「えっ?」
私の立っている背中側の壁が少しずれていた。
「押してみよう!」
真ん中を軸にぐるりと動いた。その奥から隠し部屋が現れた。
「リィン」
ジェイクがその部屋へと誘う。その部屋の突き当たりの壁が繰り抜かれて木製の棚が設けられていた。そこにいくつもの輝石が眠っていた.。
「これが、奇跡の宝玉といわれている物なのか...凄い大きさの石だな。見てみろよ、リィンの瞳の何倍もあるぜ!」
ジェイクは数ある宝玉の中でも薄紫色したアメジストを見ていた。
「あぁ、そんなに大きなアメジストは初めて見るな。」
それぞれの石が光ごけの光だけでも輝きを隠し切れずにいた。加えられた細工も見事としか言い得なかった。ダイヤモンド、サファイア、ルビーどれをっとても見事な大きさ、クオリティである。
「狙われるはずだよな、これだけの宝石がこれだけ揃ってちゃなぁ」
ジェイクは臆することなくその一つを手にとって見ていた。おそらく綺麗だては思っても、執着はないのだろう。
「何!?」
「リィン!!」
突然後ろから首をとられて剣が突きつけられた。
(誰?)そう思ってもここには三人しか居ないはず。
「宝玉を渡していただこうか!」
その声は私達のいる隠し部屋の向こうの通路からしていた。
「リィン殿、騒がずに願いたい。」
耳元で低く野太い声。
「ガルディス!?」
私に剣を突きつけていたのはガルディスだった。
「なっ、なぜだ?ガルディス!!」
ジェイクの混乱は無理もなかった。ガーディアンに入ったときからお目付け役で、長年自分の側にいた人間だ。
「ゲイル、そのままその女をこちらに連れて来い。」
隠し部屋の入り口に現れたその男はガルディスのことをゲイルと呼んだ。
「兄者...」
ゆっくりと振り返った私の目に映ったのは、銀の髪を長く伸ばして後ろで束ねた細身の背の高い壮年の男であった。
「君がアイリーンの息子か...ふん、ちっとも似てないじゃないか!あのザナックスの若い時とそっくりとは忌々しい!さあ、宝玉をすべて渡していただこうか?」
銀髪の男はゆっくりと小部屋の中へと入ってくる。
「お前は誰なんだ!?」
ジェイクは腰の剣に手をかけながらも私を気遣い、抜けずにいた。
「私か?私はレイノール。今となっては唯一の銀の王国の後継者だ。おぉ、もっともその女が死ねばだがね。くっくっく!」
レイノールの笑い声が石壁の小部屋中に響きわたる。
「レイノール、お前が!だがなぜ、ガルディスおまえがこんな奴の言いなりなんだ?」
「くっくっ、こいつは本当はゲイルといって、私の弟だよ。腹違いだがな。銀の王国の崩壊の後、病の母親を連れて困ってたとこを拾ってやったんだよ、なぁ。」
冷たい目で語る。似てる?あの男に?すでにこの手にかけた憎い敵のあの男に。そう、、このレイノールが王国を裏切り全滅させたのだ。
「すまない、ジェイク。総帥にもお目にかけていただいたのに...母の病は重く面倒を見てもらうことを条件にスパイとして入り込んだのだ。銀の王国の秘密を先取りされぬように見張るのが私の役目だった...。」
外部からガーディアンに入隊するのは容易なことではない。相当の実力、知識をともなわなければいけない。その上過酷な訓練がまちうけいるという話だ。ガルディスはその難関を乗り越え、数々の活躍で総帥の覚えもよく今の立場に取り立てられたと聞いていた。息子を預けられるほどに...。
「さあ、ジェイク!この中にその宝玉をすべて入れてもらおうか!これだけのお宝をザナックスなどに渡すわけにはいかんだろ?これを元に私が銀の王国を再建するのさ。私が王となってな!」
ジェイクは黙って放られた袋の中に宝玉をすべて収めた。
「別にこんな物、俺も親父もいらないさ。だがもう誰も残ってない王国を復活させてどうしようというんだ?」
奴のほうへと放り投げたその袋を拾い上げながら、レイノールはその冷たい目を細めて私のほうを見た。
「この銀の髪とこれらの宝玉があれば銀の一族は逆らえんのだよ。奴らが稼ぎ出す収益は王族のために使われるのだよ。ふん、だがそうだな、一人ではな。ゲイル、その女を連れて来い。」
ガルディスはジェイクのほうをちらりと見やると、私の耳元ですまないと小さく言った。レイノールの隣にまで連れられて行くと、奴はいきなり私の顎に手をかけると無理やり自分のほうに向かせた。
「男装はしているものの、中々綺麗な顔をしているじゃないか。銀の髪同士仲良くやれば銀の王国は簡単に復活するさ。我々が王となるのだ。どうだ?リィンとかいったな、お前。美しく着飾って私の側におれば贅沢はし放題だよ!」
「やめろ!離せ!宝玉も銀の王国も好きにすればいい!だがリィンだけは渡さない!」
ジェイクが小部屋の中に響き渡るほど大きな声で叫んでいた。
「頼む、ガルディス!リィンだけは...」
ジェイクの悲痛な叫びはガルディスにも向けられた。
私は自分ののど元に突きつけられている刃をちらりと見ては視線をガルディスに向けた。
「ん?どうだね?ともに王国を復活させようではないか?銀の髪だけでその権利があるのだよ?」
「嫌だね。そんな気はさらさらない。あんたがやったこと許すわけには行かないんだ。王国の生き残りとしてはね。貴様、あんな盗賊どもを使って、あんな...」
言葉が詰まる。その後をジェイクが続けてくれた。
「レイノール、おまえはあの盗賊どもは何だったんだ?いったい何をさせたんだ!」
「はっ、よくもフェルナンデスを殺してくれたよな!奴は私が幼い時、ここに来るまでに親どもが死んだ後、さ迷っていたところ拾ってくれた盗賊頭の息子だよ。私は外で生まれた王族なのでな。ちょっと冷酷な奴だがなかなかうまがあってな、ここを追い出された時も奴のとこで世話になってたんだ。ここの話をしてやったら気にいちまってな。盗賊団一党引き連れてここに押し込みやがった。ま私はここがどうなっても構わなかったがな。」
この宝玉さえあればと袋を軽く持ち上げる。そういえばおばばが、レイノールは外の一族から生まれた珍しい王族と言っていた。ここにたどり着いたのはすでに12の齢になっていたと聞く。その年ではもう銀の髪の王族の中には許婚になりえるものはもうおらず、彼のたっての希望で銀の髪でないアイリーンを望んだという。
「奴にどこまで話してたんだ!?刺青の話をしたのか?」
「ああ、したよ?だが背に彫り物があったはずの王族の娘はさっさと自害してしまってなぁ、犯し損ねてフェルの機嫌が悪くって困ったよ。くっくっく...そこで残った王族の奴らを拷問にかけてもう一人の刺青の娘を探し回ったってわけだ。16年前は取り逃がしたと聞いてあきらめたら7年ほど前だったかな?フェルから娘をみつけて犯したが刺青はなかったとまた怒らせてしまってなぁ。目印はつけたといってたがお前だったんだな。」
レイノールの手がリィンの胸元を引き裂く。白い胸元に十字の傷跡が現れる。
さすがにガルディスも目をそむける。私は...
「リィンとかいったな?これほど美しくなるんだったら私の物にしてやればよっかたよ。私はフェルと違って優しくしてやるのに、くっくっく...」
楽しくてしかったないと言った風情で雄弁に語るレイノールだったが、彼の言葉に再び過去の悪夢に引き戻され、私は唇をきつく噛み、レイノールを睨みつけていた。
(こいつがすべての元凶だったんだ!)
「きつい顔をするな。笑えばさぞ美しいだろうに。昔知ってる女によく似ていてなかなかタイプなのに惜しいな。アイリ−ンに良く似た、なんと言ったかな?あぁ、ナイジェルだ。もっともあの娘はもっと儚げなだったがな。」
(なんだって?)
「ナイジェル様はリィン殿の母君だ...兄者。」
私より先にガルディスがその名を告げた。
「はっ!あの女の!?国を出るときの置き土産に犯してやったよ!まだちと幼かったがな、はっはっは!」
「まさか...!!」
「なるほどな、計算は合いそうだな?20年ほど前だが、ナイジェルがよほどの淫乱でなければ私の娘かもしれんな!だが私は娘でも何でも構わんよ?銀の髪の子でも産んでくれればな!私はアイリーンを手に入れられないと判った時からこの国の財宝さえ手に入ればそれでいいと思えるようになったんだよ、はっはっは!」
「なっ!貴様〜〜〜〜!!」
ジェイクの目に炎が宿っていた。
(この男が私の父?すべての元凶であるこの男が?14で亡くなった母に他に男がいたとも考えられない。犯され身ごもりながらもその事実を言えなかった幼い母...)
ガルディスの剣先が緩んでいた。
「兄者、もうおやめくだされ。リィン殿が兄者のお子ならこれ以上の殺生はもう!娘と子をなど、狂っておられる!」
「私も、私もそんなのごめんだね!父親?たとえそうであっても母はその事実を誰にも伝えなかった。それは、私が母の子であっても貴様の子ではないからだ!私に父はいない。お前達に殺されたディーノ・クロスだけだ!」
きっとそのはずだ。私は奴の子ではない!たとえそうであってもこれほど憎しみの消えぬものならばそんな事実認めても何にもならないはずだ。奴はそういう人間なのだから...すでにガルディスから向けられた刃に意識はない。手は腰の剣にかかっている。ジェイクもじりじりと間合いを詰めて来る。
「リィン、構わないんだな?ガルディス、お前もこんなやつの言うことをいつまで聞いてるんだ?病の母親を見てもらっていると言ったが、本当なのか?俺にはこの男がそんな愁傷なこと続けるようには思えない。いつから会ってない?どこにいるかわかってるのか?」
ガルディスの顔色が一瞬にして青ざめるのがわかった。
「ふん、いらぬことを...」
「兄者!まさか、母は??兄者?」
レイノールは宝玉のはいった袋を手に後ずさりする。
「任務で忙しいと会いにこぬお前も悪いのだよ。偽の手紙にすっかり騙されて。もっともフェルも死んで、代筆の仲間もどこぞへいってしまってもう書くことは出来ぬがな。」
「兄者、よくも、よくも〜〜〜!!」
すでにその剣はレイノールに向けられていた。三人の剣と殺気はすべて彼に向けられていた。
「くっ!」
形勢が替わったことに気づいた奴は部屋の出口に向かって後ずさりを続ける。
「あっ!奴が!」
レイノールが走り出した。入り口は狭いので一人ずつしか出られない。ガルディス、私、ジェイクと続く。ここに入ってきた経路から考えると私たちとは違う入り口の可能性が高い。そこから逃げられたら...奴をこのまま野放しには出来ない。
「ジェイク、すまない!許してくれとはいわん。ただこの後始末だけは...」
声を詰まらせるガルディスだった。ジェイクが私を追い抜いてガルディスに並んでいた。
「兄者、いや奴は多分崖側にある別の入り口だ。そこから逃げる気だとおもう。」
「ガルディス...」
ジェイクが彼の肩をポンと叩いた。それだけで良かったのだ。たとえスパイであっても彼は今まで本当の自分でジェイクと向き合ってきたはずだ。
「リィンも構わないんだな?」
それはレイノールの死を意味する言葉だった。
奴は手に入らないものに執着し続け、己の欲と利潤のみの世界でしか生きられない男なのだ。この世に存在し続けてはいけないのだ。私は頷く。
「あぁ。」
ジェイクは私の頬をそっと撫でると、きゅっと唇を結んで前を見据えた。いつもの優しくて陽気なだけの彼ではなかった。真剣な、いや恐ろしいほど冷静で意志の強い目をしていた。
(ジェイクは自分で殺るつもりなののだろうか?)
私にはそう思えた。
洞窟を出てそのまま突き当たりまで駆けていく。左の大きな樹の陰まで行く。下ろされた縄梯子を登る奴の姿があった。
「はっ!」
ジェイクが短剣を投げつけたのだ。それは見事に奴の右肩に刺さった。それでも片手に宝玉の入った袋を放さない。そのためにバランスを崩してそれ以上上には上がれない。
「うをぉぉぉ〜〜〜〜!」
ガルディスは縄梯子を激しくゆすって奴を振り落とした。
「くそっ...ガルディス、私達は母は違うが兄弟ではないか?おぉ、リィンわが娘!ナイジェルとよく似っ!!ぐほっ!」
話すまも、与えなかった。
ジェイクの振り下ろした剣がレイノールを一刀のもとに斬りつけていた。
「き、貴様...が...」
ジェイクの目は怖いほど冷たかった。先ほどの表情に冷たさが加わっているのだ。
(この人でも、こんな目をすることがあるんだ...)
その目でじっとレイノールを見下ろしている。止めを刺すまでもなく奴は息絶えた。
私にはなんの感慨も湧いてこなかった。
ただガルディスは拳を握り締めて涙を堪えていた。
「彼も銀の王国の一員だったのだ。死してまで追い出すこともあるまい。ここに墓を作ってやろう。」
ジェイクがレイノールの亡骸を埋葬し始めた。ガルディスも黙ってそれを手伝っている。
私はそんな気にもなれずに奴が持ち出そうとしていた袋を見ていた。
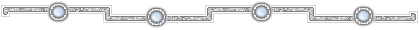
「終わったぜ。俺は先に外に出て総帥とおばばに説明してくるよ。許してはもらえんかもしれんがな...」
ガルディスはそう言うと荷物をまとめていた。
「なあ、ガルディス。お前は今ゲイルなのか?ガルディスなのか?」
「えっ?」
ジェイクの問いにガルディスは一瞬理解できなかったみたいだ。
「お前がガルディスならゲイルのことは誰にも言わなくていいさ。おまえはいつだって俺を助けてくれてた。ガルディスでいてくれるなら親父にだっていう必要ないんだ。」
「ジェイク!俺は...」
ガルディスの目には涙が浮かんでいた。厳つい顔をくしゃくしゃにして答えた。
「俺は、ガルディスだ!今までも、これからも!」
ジェイクは黙ってうなづいた。それでいいのだと。
「ジェイク、いやジェイク・R・ヒルグブルス殿」
ガルディスはひざまずき己の剣先を自らに向けジェイクに剣を捧げた。
「我、ガルディス・コーウェルは貴公に永久の忠誠を誓う!」
「ガルディス...!?」
いきなり正式な忠剣の誓いを立てられたジェイクは、一瞬戸惑いはしたもののガルディスのあまりの真剣な表情に押されて、剣の柄を取りガルディスの肩に刃を当てて、その誓いを受けた。
「ありがとうジェイク。」
彼は洞窟の通路へと戻って行った。
「なあ、ジェイク...」
「ん?」
しばらくはガルディスの去った後を心配そうに見ていた彼だった。
「この宝玉、このままここに置いていっちゃいけないかな?」
「えっ?」
「べつにこんな物欲しくもないし、持っていたってそれで王国がどうとも思わないんだが...」
「けれども一族が困った時に使えるぞ?」
「その時は自分の力で助けたいと思う。だめかな?」
うーんとジェイクも考え込む。
「リィンがまた狙われるぞ?その背中の謎を欲しがる奴がきっと出てくるぞ?」
「あぁ、だけどその時は護ってくれるんだろ?ジェイクが。もちろんわたしもこの背中をお前以外に見せる気はないが...」
立ち上がって、ジェイクの目を覗き込んでみる。
「当たり前だ!俺が護って見せるさ!命に代えても!」
「だめだよ。」
私は静かに言った。
「ジェイクが死んでしまったらもう護れなくなるだろ?その後どうするんだ?」
「うっ、それは...」
言葉に詰まって考え込んでいる。
「連れて行けよ。どこまでも、死の国までも、な?それともそこまで自信ないのか?」
わたしはくすくすと笑いながら聞いてやる。もう過去にも、なににも囚われることはないのだから。今目の前にいるこの人だけなのだ。私を捉えているのは...だから宝玉もここに捨てて行きたかった。
「もちろん!自信あるさ!その、リィンさえ一緒にいてくれれば...」
そのままジェイクの胸に寄りかかる。彼の腕が私を捉える。
「離さない...たとえリィンが嫌がってもな。」
きつくその胸に抱きしめられる。軽く顎を持ち上げられるとジェイクの唇が落ちてきた。
深い口付けは長い時間続いた。
Back・Next
>Home>NovelTop>Top


![]()